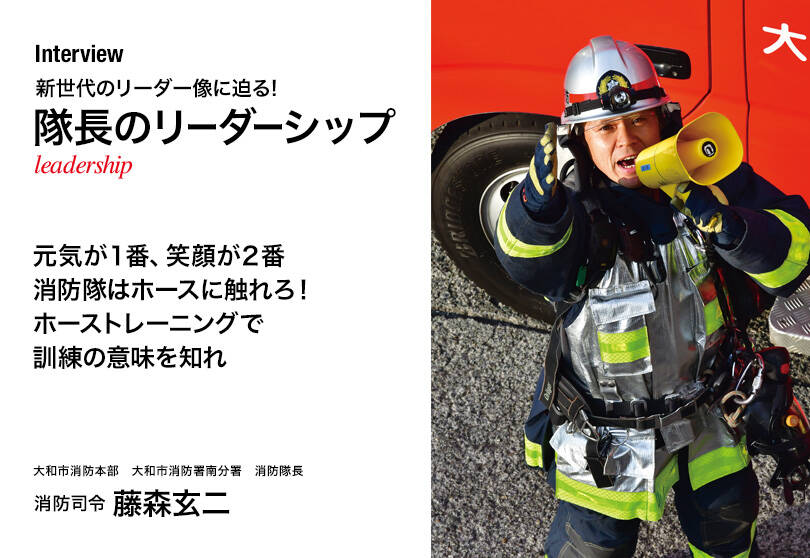富士山大規模噴火に備える
東京消防庁が生んだ“かつてない救助車”
東京消防庁は富士山大規模に備え2025年(令和7年)3月7日、第九消防方面本部消防救助機動部隊に「救助救助車(道路啓開型)」を配備した。
写真◎編集部
日本の消防車2026掲載記事
灰に埋もれた道を切り開け
東京を支える走る力
2020年(令和2年)4月に国の中央防災会議の「大規模噴火時の広域降灰対策検討ワーキンググループ」において、富士山が大規模噴火し大量の火山灰が首都圏に降った際、東京都多摩地区には最大30cm、特別区においては最大10cmの火山灰が堆積すると予測されており、都市機能に深刻な影響を与えることが報告された。
これを受けて東京消防庁では、2021年(令和3年11月)に山梨県が主催した火山灰上の走行体験事業および令和5年度に東京都の富士山噴火降灰対策検討会の作業部会が実施した除灰実験に参加した。
走行実験では、二輪駆動の消防ポンプ自動車や救助車に走行障害が発生し、降灰が一定量堆積すると消防車両の迅速な現場到着が困難になることが判明し、喫緊で解決しなければならない課題が浮き彫りになった。
これらの実証実験を受けて同庁では、令和5年度から各消防署に配置している査察広報車(ワンボックス型)を四輪駆動化し、消防ポンプ自動車が運行不能になった際に可搬式動力消防ポンプを積載して出場することで、東京都全域において応急的に災害対応が可能な体制を整えている。
令和6年度は、大きな被害が予想される多摩地区の災害対応力を維持することを目的に救出救助車(道路啓開型)を増強整備することとし、第九消防方面本部消防救助機動部隊(以下、九本部ハイパー)に配備した。

悪路に強いシャーシ「ウニモグ」を採用
降灰が道路に堆積した際の除灰作業は、主に道路管理者が実施するが、東京都の計画では、重要拠点を連絡する道路(以下、優先除灰道路という)を優先的に除灰する計画になっている。
そのため、同庁では優先除灰道路以外の住宅地域等で火災や救急等の災害が発生した場合においても迅速に現場に到着できるよう、必要な啓開活動体制を整える必要がある。
道路啓開用の車両としてホイールローダーやドラグショベル等はすでに保有しているが、いずれも公道を走行できず局所的な対応しかできなかったことから、公道走行可能で、なおかつ同庁で即応対処部隊が保有しているメルセデス・ベンツ社製の「ウニモグ」をベースシャーシとした高機動型救助車よりも小型である多目的型のウニモグを基本シャーシとすることで、消防署所から指令先までの道路を広域的に除灰ができる体制を整備した。

走破性を高めるために「圧縮空気取出装置」を採用
同庁において、火山災害で活動した記録は、2000年(平成12年)の三宅島噴火、2014年(平成26年)の御嶽山噴火などがある。いずれの活動も水分を含んだ粘土のような火山灰が高い活動障害になったほか、火山性ガスによる視界不良、火山灰の酸性成分による消防車両の腐食、鉱物片によるタイヤの損傷、さらには、再噴火への隊員の心理的不安など、非常に困難な活動であったと記録されている。
これらの知見を踏まえ、同庁で前例のない活動に対して必要な性能を有する仕様とする必要があった。
具体的には、排土板の仕様検討が挙げられる。排土板には雪用、土砂用があるが降灰専用のものはない。形状もストレート型、V型がある。そこで本車両の排土板は、形状はV型とし、万が一、排土板のアングリング用油圧シリンダーが短縮してもV字の形状を保ち火山灰を左右にかき分けて走行できるようにした。
また、走破性を高めるために「圧縮空気取出装置」を採用している。これは、シャーシのエアーブレーキタンクから圧縮空気を取り出すもので、ラジエータのフィンやエアークリーナーに付着した火山灰を除去できるほか、タイヤの空気を充填することもできる。火山灰上での走破性を高めるためには、タイヤの空気を一時的に抜き接地面積を増やすとともに、タイヤの変形によりトレッド面に付着した火山灰を落とすセルフクリーニングの効果がある。

次のページ:
ギミックや運転席の内部を紹介!