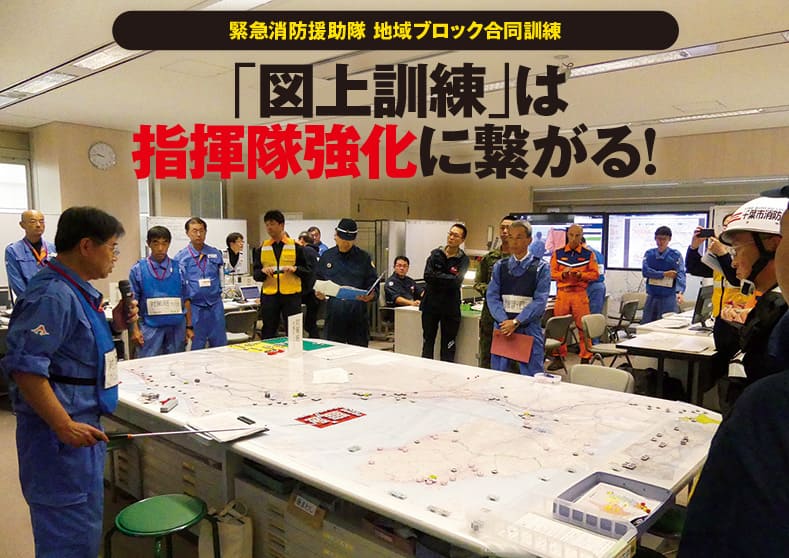髙山 幸夫 Takayama Yukio
Takayama Yukio
Interview
元ハイパーレスキュー総括隊長に聞く
【チーム作り】と【これからの安全管理】
止める勇気こそ、
リーダーに必要なもの
リーダーに必要なもの
――髙山さんといえば、東日本大震災で福島第一原発に出場し、決死の放水活動の現場指揮をとった一人。あの時の臨時チーム編成の経緯や指揮官として当時どんなことを考えておられたのでしょうか。
福島に出場したのは平成23年3月17日。11日の地震発生日から7日目だった。発災の日は当直明けで、結婚記念日でもあったので、午前中には帰って何かプレゼントでもと考えていたが、たまたま運用する重機に不具合が生じたため、修理業者を待っていたところで地震が発生した。当然、我が8本部ハイパーレスキューにはすぐに出場指令が下るものと全隊員で出場準備を進めていたが、他の方面部隊には順に出場が入るものの、8本部にはなかなか指令が下らない。東京消防庁としては、都内を守る部隊を残す意図があったのだろう。そうこうしている間に福島第一原発の爆発事故が発生した。そうなると部隊の責任者としては、隊員をそんな危険な場所に出場させたくない、と考えが一変した。しかし、自衛隊や警察の放水冷却活動がなかなか上手くいっていないことから、万が一出場することになった場合に備え、原発施設への放水を想定した訓練の招集がかかった。
「隊員は8本部に戻らずに、そのまま福島へ出場してしまうのではないか」と心配していたが、隊員らは夜遅くにいったんは8本部に戻った。しかし、深夜に東京都知事の要請があり東京消防庁から部隊に出場指令が下った。私の任務は隊員32名を選出してともに出場すること。上司に相談すると、「人選は総括に任せる」と一任された。
――大量被ばくの危険性の高い、まさに命がけの出場であり、国の窮地を救えるかどうかという最重要任務ですよね。
人選にあっては、まず隊長9名は全員出場させることを即断した。問題は残るメンバーだが、被ばくによる健康被害を考えれば、「あいつは子供がまだ小さい」「あいつはもう一人子供が欲しいと言っていた」など人間としての情が入ってしまう。しかし、それでは失敗できない重要ミッションを速やかに遂行するための人選ができないため、情を一切排除して人選することにした。
――最終的に出場メンバーを選んだ決定打は何だったのですか?
基準はたった一つ。「気が利く」かどうかだった。ふだんから気が利く者は現場でも気が利く。ふだん気が利かない者は、現場でも気が利かないものだ。これは、30年近くレスキューの世界に身を置いた自分の経験値から導き出した判断基準だった。福島第一原発のような切迫した現場で、現場の状況が不明瞭かつ、どのような活動になるかも定かでなく、しかも混成部隊で活動する際に必要とされるのは、柔軟に先回りして動ける「気働き」ができる者だったのだ。
――特別救助隊という選び抜かれた厳しい世界にいる者ならだれもが気が利くというわけではないのですか?
ハイパーレスキューの者なら、全員が何も言わずとも動けるのかというと、決してそんなことはない。気が利くというのは、誰かに教わることで身に付くようなものではないし、とりわけ若い隊員に足りない部分なのではないかと感じている。私も現役時代は若い隊員によく、「トンカチを持ってこいと言ったら釘も持ってくるのが当たり前だよ」と言ったものだが、気が利くとはそういうことなのだ。一つのことを言われたら、それは何に使うものなのか、そのために何が必要なのかまで考えなければならない。お酒の席等で、先輩や隊長のグラスが空いたらすぐお酒を注げるかどうかという部分でもそれはわかる。部下の気遣いに気づいた時は、その場で褒めることも大事。ダメなものはダメと叱るばかりでなく、褒めて育てることも大切だと思う。
――福島第一原発の放水作戦では、活動中に隊員の個人線量計のアラームが鳴り響いていましたが、どの段階まできたら撤退するかは決めていたのですか?
福島に向かう道中、「出来ないことは出来ないとはっきり言おう」と心に決めていた。それが自分の仕事だと。だが、いざ現場に入ってしまうと、「やるしかない」という使命感から、途中で止めるという選択肢がなくなっていた。放水自体はうまくいったが、一歩間違えたら、とんでもない事故になるという危機感が常にあった。被ばくの影響が活動直後に出た職員はいなかったが、放射線は目に見えず、はっきり判定されにくいグレーな活動だった。あの時、たとえ私が活動を途中で放り出して撤退すべきと思ったとしても、撤退を決める権限が自分にあったのかどうかは定かでない。その選択をすべきだったのかはいまだに悩むところだ。これに限らず、どんな災害対応においても、人生を棒に振ってしまうような危険を冒してまで行う活動は、指揮官としてやらせてはいけないと考えている。
最近はスポーツ界でも、高校野球のある学校で、エースの投手の将来性を考えて投げさせなかったことが賛否を呼んだが、自分を犠牲にすることを美徳とする根本理論は覆さなければならない。消防の指揮官もこれからは、気合と根性論だけではダメだと思う。隊員らはみな、それは言わなくても持っているし、「大丈夫か」と聞いて「ダメです」と答える者はいない。だから、これからの指揮官は、あえて「逃げる」選択をする勇気を持ち、「待て」と「止め」を自信をもって命令できなければならないと、批判を覚悟で思う。そうでなければ、隊員を守れないからだ。
安全管理は、ハードの
アップデートからやるべき
アップデートからやるべき
――今年は、とりわけ消防職員の活動中の死傷事故が発生していますが、安全管理面でどんなところを見直していくべきだと思いますか?
東京消防庁を退職後、民間企業で働いてみて、「安全」に対する民間の徹底した取り組みに驚かされた。まず、高さ2メートル以上の高所で作業を行う場合は、社員はもちろん、外部の委託業者であっても必ずフルボディハーネスを装着するということが徹底されている。次に、会社の敷地内の道を渡る際は、誰も見ていなくても、全員が指さし呼称で左右の安全を確認するほか、階段を降りるときは必ず手すりを持つということを社員全員が守っている。
事故が発生した後の対策にも見習うべき点があった。ある時、壁に付いたタラップ状のはしごから足を踏み外して社員が転倒するという事故があった。この後に会社が講じた対策は、すべてのタラップを階段タイプに付け替えることだった。どんな人が使用したとしても同じような事故が起こらないように、ハード面で具体的な対策を講じたのである。これには大いに学ぶべきところがあると感じた。
とはいえ、消防活動は安全第一ではない。逃げ遅れた人の安全が第一である。隊員の安全優先で現場から逃げていたら仕事にならない。異常で危険なのが災害現場であり、だからこそ消防の出番なのだ。だからといって、命を捨てて火の中に飛び込めと言っているのではない。安全確保は人命救助という目的達成のための大前提。その「大前提」を確保するためには、人間の力に左右されないハード対策でガッチリ固めることが喫緊の課題であると考える。文書などでいくら注意喚起を促しても、ミスをしない人間はいないのだから。消防の使命達成と安全管理の両立は永遠のテーマである。最近のいろいろな事故の報に触れ、退職後もそう感じている。